
博多の町を流れる石堂川(御笠川)の横に流区域があったことから、かつては「石堂流」と呼ばれていましたが、博多松囃子(どんたく)の"恵比須流"とほぼ流区域を同じとしているため、これにちなんで山笠の流名も「恵比須流」となりました。
博多の中心部にも飛び石的に構成町がありますが、主地盤は御笠川の西岸一帯。近年、"都心のドーナツ化現象"で人口が減少。舁き手不足が深刻化していましたが、旧大浜小学校のPTAなどの協力を得て克服しています。
閻魔大王は言わずと知れた地獄の裁判官で、送られてきた死者の生前の罪を裁きます。その鋭い眼光はすべての罪を見通し、いかなるものもこの閻魔大王の目を欺くことは出来ません。
しかし、閻魔大王が地蔵菩薩の化身であることも忘れてはなりません。その世界を照らす眼光は、慈悲の光を湛えいつも私たちを見守っているののです。
「眼光」は文字通り目の光のこととですが、あらゆる真実を見通す力のことも意味します。「照破」とは、どこもかしこも照らしぬくこと。「四天下」とは、「須弥山(しゅみせん)の四方にある四大州(しだいしゅう)[南瞻部(なんせん)州・東勝身(とうしょうしん)州、西牛貨(さいごけ)州・北倶盧(ほっくる)州]」のことで、すべての世界の意味です。
[人形師:人形司武平]
福岡市営地下鉄「呉服町」より徒歩6分
西鉄バス「石堂大橋」下車より徒歩5分
| 7/1 (月) |
7/9 (火) |
7/10 (水) |
7/11 (木) |
7/12 (金) |
7/13 (土) |
7/14 (日) |
7/15 (月祝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当番町 お汐井取り |
全町 お汐井取り |
流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし |
集団 山見せ |
流舁 | 追い山 |
| 17:55 | 17:55 | 18:00 | 5:00 | - | 町舁出 14:05 山列入 14:25 櫛田入 16:25 |
町舁出 14:35 山列入 14:55 始点出発 15:55 |
16:00 | 町舁出 1:35 山列入 1:55 櫛田入 5:25 |
※お汐井取りの時刻は、石堂橋の出発時刻
より大きな地図で 博多祇園山笠 「流」エリアマップ【山笠ナビ】 を表示
 下竪町
下竪町
 下金屋町
下金屋町
 横町
横町
 上金屋町
上金屋町
 官内町
官内町
 上竪町
上竪町
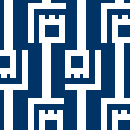 中石堂町
中石堂町
 中間町
中間町
 蓮池町
蓮池町
 綱場町
綱場町
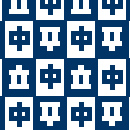 中竪町
中竪町
 下竪町
下竪町
 下金屋町
下金屋町
 横町
横町
 上金屋町
上金屋町
 官内町
官内町
 上竪町
上竪町
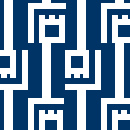 中石堂町
中石堂町
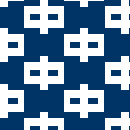 中間町
中間町
 蓮池町
蓮池町
 綱場町
綱場町
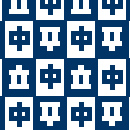 中竪町
中竪町