
博多の幹線道路・大博通りの西側が流域。博多地区の町界町名整理事業後、旧西町流に旧岡流、旧櫛田流、旧呉服町流が合流して「西流」として発足しました。
非常に広い町内が多く、また流域内にはオフィスビルも多いため、山笠に魅了されて参加を決意するサラリーマンや転勤族も多く、古くからの地元住民とあわせて参加人数も非常に多い流です。
山笠の伝統でもある道路上に山小屋を建てる事や(※当番町の道路幅の状況によります)、山崩しを唯一行っている流でもあります。水法被、当番法被(長法被)ともに、各町毎にデザインが異なります。
一五八七年(天正十五年)九州征伐の途次、豊臣秀吉は博多の街のさらなる繁栄を願い、大掛かりな町割りを行いました。その際、秀吉が滞在した地に、豊国神社が鎮座していると伝わっております。
聖一国師による悪疫退散の祈祷行脚に起源を持つ山笠は、博多の街の安寧を願う神事であります。現在、太閤町割りと呼ばれる政を行った秀吉もまた、街の再整理によって博多の繁栄と安寧を願った一人です。夢、遙かに大海を望む。
九州平定を前に、博多の地を訪れた秀吉は、古くから外つ国へと開かれたこの博多の海を望み、天下統一というみずからの夢を、その胸に熱く刻んだことでしょう。
混迷を深める現代において、博多の街だけではなく、世界の安寧と繁栄を願う。その一念から、大海を望み大いなる夢に想いを馳せる秀吉の姿に私たちの願いを託さんと思い、今年の表題といたしました。
[人形師:西川直樹]
福岡市営地下鉄「呉服町」より徒歩5分
西鉄バス停「蔵本」より徒歩1分
| 7/1 (月) |
7/9 (火) |
7/10 (水) |
7/11 (木) |
7/12 (金) |
7/13 (土) |
7/14 (日) |
7/15 (月祝) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当番町 お汐井取り |
全町 お汐井取り |
流舁 | 朝山 | 他流舁 | 追い山 ならし |
集団 山見せ |
流舁 | 追い山 |
| 17:45 | 17:45 | 17:00 | 5:00 | - | 町舁出 13:50 山列入 14:15 櫛田入 16:15 |
町舁出 14:25 山列入 14:45 始点出発 15:45 |
17:00 | 町舁出 1:20 山列入 1:45 櫛田入 5:15 |
※お汐井取りの時刻は、石堂橋の出発時刻
より大きな地図で 博多祇園山笠 「流」エリアマップ【山笠ナビ】 を表示
 冷泉上
冷泉上
 冷泉下
冷泉下
 店屋町
店屋町
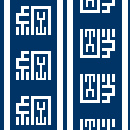 綱場町
綱場町
 奈良屋町
奈良屋町
 冷泉上
冷泉上
 冷泉下
冷泉下
 店屋町
店屋町
 綱場町
綱場町
 奈良屋町
奈良屋町